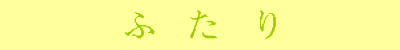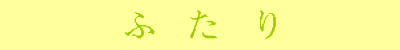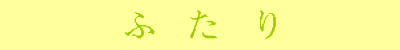
【ふたり】
「貴方、何をそんなに急いでいるの?」
私は先を夢中に急ぐ彼に尋ねる。石畳を軽快に踏み進む彼は、後ろを振り返って目を細めた。
白髪交じりの、しかし五十代前半にしては黒い草が十二部に茂っている頭をぽりぽりと掻き
ながら、わざとらしくお茶目な素振りを見せてくれる。全く、仕事から帰ってきたときはそん
な表情なんて簡単には見せてはくれないのに。私が忘れてしまった頃に、古めかしいアルバム
を捲って懐かしく想うように。貴方は突然、柔らかく崩れた顔つきをして私を驚かすのね。
「すまないね。この先に木村屋という人形焼の美味しい御店があるから」
「中年太りしている中年の私を、これ以上太らせようというの?」
皺の寄っている顔を綻ばせて冗談を言えば、彼はその通りだよとまた私の前を歩いていく。
対面する群集を見事縦に割りながら、しかし落ち着いた足取りで両手を体の後ろで組んでい
る。紺色のジャケットを着ている背中は、若かりし日に比べたら、そりゃあすっかり丸まって
いて、老いを感じさせないとは言わせなかった。でも私はどれだけこの広い広い背中に縋り寄
ったことだろうか。日曜日の昼下がり、人々を一層賑やかにする晴れ空を拝んでみても、私に
は分からない。
「もう少しだから。ほらっ」
体の後ろで組んでいた両手を私にちらつかせ、強調している。私は思い切り彼に、甘えるこ
とにした。大きくて大きくて私のちっぽけな掌なんか容易く包んでしまう、温もりのある其れ
は、優しく私を引いた。引いていく。この浅草寺へと続く長い仲見世通りの中、私が何十年と
培って来た貴方への一途な想いも一緒に。馬鹿と呼びたければどうぞ。私の気持ちはまだ、新
婚二日目よ。まだまだ年老いてはいないわ。
「着いたよ」
感慨深げに、掌の仄かな暖かさに染み入っていたらいつの間にか目的の御店に辿り着いた。
仲見世通りを抜ける直前、堂々と看板に人形焼元祖木村屋と書かれている。評判高い御店な
のか、多くの観光客が足を止めては「一六個入り、三つ」などと口々に店頭に立つ若いお兄さ
んに伝えている。しかし何故か、目的地に着いた実感は何時しか寂しさへと変わっていた。
「ん、どうした?」
私は彼のジャケットを引っ張って、静止を促した。
「ねぇ、この歳になってこんな事言うの恥ずかしいけれど、もうちょっとだけ……」
手をつないでいて欲しいわ。
仲見世通りを過ぎた先は、浅草寺の広場。疎らに散った群衆をもはや掻き分けながら進む必
要は無くなっていた。彼は私の発言の可笑しさにまだ笑っている。それでも私の掌だけは、し
っかりと握り締めてくれていて、泣きそうになった。私は彼の後ろすぐを歩いている。もうち
ょっとだけ甘えさせて。昼下がりはまだまだ長いわ。おやつを食べるには、きっとまだ早いだ
ろうから、手をつないで歩いていたい。
「お前の気が済むまで、歩いてあげよう。だからしっかりとついておいで」
私の我が侭に対するお返しは、明るく振舞う彼の囁き。私は当分の間は、この温もりを手放
したくはなかった。迫りくる月曜日という憂鬱から逃れるみたいに、私と彼はもう少しだけ、
歩いていることにした。泣いてしまうのを見られないように、彼の背中に顔をうずめながら。
【君と私と正装と】
私達の国との国交が著しい隣国の皇女とグラスを交わして談笑していただけなのに、恨め
しく思った君は、煌く黄金のシャンデリア達の下を駆けていった。ピアノと心地の良い管弦
楽の協奏に浸っていた人々の間を潜り抜けて行き、息も尽かさぬままに大理石の床にハイヒ
ールを打ち鳴らして、立食会が行われている大広間の扉を、突破するように開けて出て行く。
何事かと騒然する会場。胸に数え切れない勲章と、立派な髭を蓄えていらっしゃる首席宰
相が掌でジャスチャーを交えながら、他の正装している男性に話し掛ければ、その男性は今
起きた状況に困ったように首を傾げている。そのような光景があちらこちらで見られた。
「すみません。妻を捜して参りますので……失礼」
呆然と、しかし怪訝な表情で口を半開きにしている皇女に軽く会釈すると、林檎ジュース
がまだ半分残っている長細いグラスを、近くにいるスタッフの持つトレイに戻し、失礼など
省みずに、私も駆け出した。様々な国際語が飛び交う中を、私は点在する白いクロスに覆わ
れている丸テーブルを確実に避けて、大広間を後にした。
「何処に?」
華やかな灯火が幾層もあるシャンデリアのおかげで明るかった立食会場とはうって変わっ
て、長く長くそして広々としている廊下は、少しだけ物足りない気がした。目に飛び込んで
きたのは大広間の扉のある壁とは正反対の外側、宮殿の中庭を展望できる白い枠で囲まれた
硝子窓。すると雲間から日差しが覗き込み、油断していた私の視界を白くする。薄暗さ抜群
の廊下に斜光が何本も照って、見事な明るさを演出した。あぁ、このまま私の心の中の曇天
模様も払底してくれるなら、どんなに救われることか。斜光の一本を全身に浴び、ライトア
ップされている舞台俳優のようになりながら、ほんの少しだけ胸を軋ませる。そして苦笑が
漏れる。
「いつもこうです。すぐに機嫌を損ねてしまうのだから」
思い出して、起毛している赤絨毯が敷かれた廊下を歩き出す。きっと君はまた、木漏れ日
が仄かに輝く裏庭で私を待っている。激務は何時になったら終わるのよ、胃がキリキリする
のよ、作り笑いが上手くなったって何の得にもなりはしないのよ、なんて両耳をゴッホみた
く切り落としたい気分に駆られる勢いの愚痴を、延々と聞かされる。私は赤絨毯を踏みしめ
中途半端な高さで消された蝋燭が乗る鉄の燭台を、ふと見上げた。下唇を噛み、肩を震わし
て、拳を震える程に強く握り締めた。このままではいけない。こんな、溶け切れてはいない
蝋燭のようでは駄目だ。最後までしっかり灯を点す役割を果たさなければいけない。途中で
消えていては意味がない。廊下の壁に掛けられている燭台を睨みつけた。
「私は、私のちっぽけな灯火を消す訳にはいかない」
正装された服装。ロープネクタイを締め直し、胸ポケットから出ているハンカチーフを整
わせると、私は歩を進ませる。行き先は唯一つ、裏庭にある大理石の噴水前。足取りも軽い。
何だか走りたくなってきた。君に早く会いたい、不器用だけれど謝りたい。足音の間隔が
狭くなってきて私はとうとう走り出した。また胸ポケットのハンカチーフが乱れてきたけれ
ども、今は一心不乱に君に会いに行く。ただそれだけの気持ちを携えて。
*
「……これ。差しておかないと日に焼けてしまいますよ?」
鬱蒼とした、しかし存分に光が浸入している裏庭で、君は寂しく縮こまっていた。緑の蔦
が宮殿の外壁を無造作に伝っている不気味さとは対照的に、せせらぎが心地良い、大理石で
形作られている白い噴水がポツリと点在している。噴出された水を溜め込む池部分にある、
白馬や騎士を模った彫刻が何だか眩しい。存在が突出している噴水に、守って貰いたいのか、
君はその傍に寄ったまま、しゃがみ込んでいる。
「今日はですね、気温が例年より五℃高いそうです。暑くなりますね」
私はたまたま玄関口の隅に横たわっていた、黒い日傘を拾っていた。何方の物かは存じな
いが、ちょっと御拝借。私はズボンのポケットから、徐に真っ白な手袋を取り出し、両手に
嵌めた。そして、日傘を静かに差す。芝生をシャクシャク踏み締めて、私は差したまま歩み
寄る。君は微動だにせず、さらに小さく小さく縮んでいた。様子を覗うように首を横に傾げ
何気無く微笑んでみても、膝を抱えて頭を埋めている君は其れを見る訳が無かった。今日は
各国の首脳陣を招いての昼食会。立派な公務なのだからと、私は渋い顔で拒もうとも拒みき
れない君の意思を押し通し、純潔を表す真っ白な絹から作られたドレスを身に纏わせた。今
は泥で薄く汚れてはいるけれど、私と君との悲しみの前では、余りにも些細過ぎている。
「ほら。これで大丈夫」
塞がっている君の体の真上を、黒い模様で覆い尽くした。少し、私の体もしゃがませては
同じ視線になるように心掛ける。が、目に飛び込んでくるのは、しなやかに曲げられている
何も語らない白い背中。躊躇しながらも私はソッと手を伸ばし、肩に柔らかく添えた。途端
に痙攣でも起こしたかのように、全身を震わせた。こんな私に対して、君は怯えていると訴
えるのだろうか。咄嗟に顔を逸らして、私は双眸を尖らせる。触れることも容赦してくれは
しないまでに、君の精神をボロボロにしてしまっている私が情けなかった。
「……私がそんなに君を台無しにしてしまうのなら、無理はしなくても良いのですよ。私は
君の傍から離れます。ただ、どうか日傘だけは受け取ってください」
会釈をして、そのまま日傘を君に差し出す。でも、受け取ってくれないのは最初から察し
ていたから、迷い戸惑う想いと一緒に君の横に置くのだ。ぎくしゃくして、私は重い腰を上
げる。
「ごめんなさい。……もし、もしもね、君が私に愛想を尽かせて、他の男性を好きになった
としても、私は止めません。それで、公務のストレスから解放されるなら、喜んで受け入れ
ますから。……ごめんなさい。私は君の気持ちなんて、これっぽっちも理解してはいなかった」
語尾がだんだんと弱く霞んでいった。私はすっかり打ちのめされて、顔を俯かせる。私が
居ない方が良いのではないかと言動で示すも、体は突っ立っているだけで動かない。
「……ごめんなさい」
生粋の不器用で、ごめんなさいの一言しか浮かばない私が実に忌々しかった。適切な言葉
は広い世の中、ごまんと存在するのは承知しているが、世界にたった一つでもある筈の、君
を救える台詞を、探し当てるのは困難だった。今一度、拳を握り締めて、深々と頭を下げる。
ずっと丸い背中しか見せてはくれなかった君に、己を恥じながら深々と頭を下げた。
「…………」
「それでもね、好きです。大好きです。……私の妻でいてくれて、ありがとう」
でも素直な気持ちは誰にも負けないから、私は君にもう一度だけ触れて釈明したかったけ
れども、自分に正直でありたいと思う。君が振り返ってはくれなくても、ありがとうに私の
君に対する誠実さを込めた。
ファッションデザイナーを目指していた君は、スクールの皇族服飾の研修で私に出会い、
同い年と気づけばお互いに惹かれあう仲になっていた。そろそろ良い時期だろうと決心した
のは十八歳の時で、無論父さん……天皇陛下は苦い顔をしていた。でも、お人好しで声を大
きくして反対を唱えなかった。母さんは、若いって本当に良いわねと、笑いながらグリーン
ティーを啜っていた。今考えればもう少し反対があったほうが、冷静に状況を見極められた
のではないかと後悔している。皇族が担う公務がいかに激しく、時間に追われるものか、君
に話す時間をじっくり設ければ良かった。でもそのまま突っ走って結ばれて、瞬く間に一年
が過ぎていった。歳は共々、十九歳になったばかり。あの頃、私と貴方はまだまだ未熟だっ
たのよ、今もきっとそうなのよ。私と二人っきりになる度に、君が必ずぼやいていた。
「待っています。自分勝手でどうしようもない私ですけれど、君を待っています」
矛盾していると思いつつも覚束なく踵を翻して、暫く煉瓦花壇に植えられている草花を意
味も無く、しかし締めつけられる気分で見据えた。もしかして私と結ばれなければ、今頃は
デザイナーで、皇族の公務よりも余裕のある生活になっていたかもしれない。きっとその道
の人と結ばれれば、互いに共通の目標が持てて、心も晴れやかに充実出来る筈ではないか。
背中姿でも君を見つめていると、君一直線で、私にとって都合の悪い考えは頭に入ってき
やしない。しかし、いざ君から目を離し、何の変哲も無い風景に見向けば、頭の隅に固まっ
ている私を悩ます要因が湧き水のように溢れ出す。
「あぁ、そういえば……」
私は聞こえないように、呟いた。黒々とした正装の上着をマジマジと眺める。生地も上質
で、自然な光沢が麗しい。裁断もハサミを使用しているのに歪み無く、整っているライン。
縫い付けもボタンに至るまで、しっかり抜かりなく縫われており、着心地もまるで布の形
をした精密機械みたく、見事に体に馴染んでいる。これは全て君が私のオーダーに応えてく
れたもの。嫌だ嫌だと拒まずに。私が朝、目を覚まし、クローゼットを開けると掛けてあっ
たその苦労の塊を、当たり前のように平然と着こなしている自分は阿呆だった。両腕を交差
し、自らの肩を抱く。吐く息が苦しい。こんな無神経な男が、女性一人を悲しませるくらい
恐ろしく容易かった。
「私には、貴方以外にいないのよ」
「えっ!?」
急に後ろから刺された言葉に、私は吃驚しつつ反応を示した。慌てて振り返ってみると、
頭を垂れて膝立ちをしている君。駆け寄って、汚れますよと手を差し伸べる。頷き、君も手
を差し出す。差し出された掌を、愛しく握り締める。
「立てますか?」
「はい」
立ち上がるや否や、私は君の体を引き寄せる。君は全く拒まずに、私の背中に腕を回した。
「私も謝らなくてはいけないわね。ごめんなさい。私も所詮、くだらない皇太妃よ。すぐ頭
に血が上っては、貴方を全否定してしまうから」
「……」
私に非があるのに、こっちにも非があると訴えかける君の優しさは、今の私には辛くて堪
らなかった。ふいに、君が腕の力を緩めるものだから、その腕を私の背中から取り外す。両
腕を掴んだまま黙り込んでいたら、君が優しく笑いかける。恥ずかしくなって、顔を左下に
向けてしまうと、君は冗談半分に私の頬を抓った。「痛い!」と私が大袈裟に声を荒げれば
君はクスクス、口元で笑う。丁度、逆光で見えにくかった。けれども、太陽を背に誇らしげ
に、邪心の無い笑みを浮かべる君はもっと煌々としていて、私を盲目にしてしまうよ。
「……映画」
「うん?」
「映画を、観にいけないかしら。リバイバル上映のローマの休日」
私と同じように、真っ赤に茹だって蒸気を放つ君に私は何も言わずに、噴水の傍らに転が
っている日傘を取り上げる。したらば、柄を掴み思い切り広げた。
「言ったばかりではないですか。私は君を待っていると。だから、君が行きたいと言ってく
れれば、精一杯応えますよ。それも立派な公務なのですから、私のオードリー」
君の真横に体をつけ、二人の頭上に真っ黒い蝶の模様が飛び交っている。足並みを揃えて
一つの傘の下の一組の未熟な夫婦は、静かに歩き出した。私のオードリーという最後のくど
過ぎる付け足しに、笑い飛ばされてしまうのではないか不安ではあったが、君はとても嬉し
そうで、真っ直ぐ前だけを見据えている。私も胸弾み、手を繋ごうとした。くすぐったいの
か、体をソワソワさせながらも指を絡めてくれる。
裏庭を抜ける頃、管弦楽のメロディーが耳に纏わりつき始めた。玄関に到着し、赤絨毯の
感触に思い起こされ、心配になって君を横目で恐る恐る確認する。やっぱり、体に余計な力
が加わっていた。大丈夫ですか。私が声を掛ける。オードリーの演じていた王女の気持ちが
良く分かるわ。君は顔を強張らせ、涙目になっている。私は長く長く、永遠と錯覚してしま
うような廊下に立ち向かう決意をする。君の耳元で、立ち向かう決意をした。もうちょっと
だけ、皇族で居てください。でも、デザイナーを目指している君を応援しますよ。私の一張
羅は、君の大切な夢の欠片です。欠片がいつか結晶になるまでは……。
私がついていますよ。ずっとずっと。
【ルージュの伝言】 Original:Yuming
洋服も下着も長居する覚悟も全て詰まった鞄を提げながら、私は一七時発のベルリン行き
に駆け込んだ。駅構内に黒く轟く汽笛を叫ぶと、汽車はゆっくりと各号車を引っ張り出す。
さよなら、ダーリン。
私は指定席に座って、優々と故郷を旅立つわ。夕闇迫る時間帯、ちらほらとライトを点灯
している車と人ごみを汽車は、並んでは抜いていく。不安な気持ちは、もうとっくに貴方と
私の家に置いてけぼりにしたつもりなのに、今も怖くて怖くて仕方が無いわ。膝の上で鞄を
抱えている腕は、あらら……力が入りすぎて赤く染まっているわ。
街はどんどん遠ざかる。
浮気癖が治らないのは若い頃から変わらないわね。変わらないなら変わらせるまでよ。風
景は忙しない街から、単調な林道へと移り変わるけれど、私も負けないわ。きっと、貴方の
ママのお家に着くのは明日の明け方。日の出と共に駅に着き、バスで向かえばあっという間。
マザーコンプレックスの貴方は驚くでしょうね。泣きじゃくって家に飛び込めば、ママは
きっとカンカンよ!
朝一番の電話口で冷や汗一杯の貴方を想いながら、私は今日も平凡に沈む夕陽を拝む。そ
ろそろバスルームに残した伝言に気づく頃ね。私の愛用するルージュで思い切り書き殴った
伝言に、きっと後悔するわ。でもでも、それは貴方を愛しているから。嫌いだったら、さっ
さとバイバイしている。ママからの電話で反省した暁には、貴方が大好きなホットケーキを
山のように焼いてあげるわね。美味しい美味しいとリスのように、ほっぺたを膨らますキュ
ートな貴方を早く見たいから、私は貴方のママに会いに行くわ。
待ってて、ダーリン。
汽車は思った以上に速くて、でもベルリンは思った以上に遠くて、ホットケーキじゃなく
て不安な気持ちは膨らむ一方で。夕闇の葡萄畑が広がる田園に、ポツリと明かりが漏れる一
軒家がとっても暖かそう。私は早くもホームシックよ!
バスルームの鏡に残した伝言。
それを初めて見て驚愕する貴方の表情を思い浮かべながら、私は頬杖をついて瞳を閉じた。
『私の堪忍袋はもう限界! 明日の朝を楽しみにしていてちょうだい、My Darling』
おやすみ、ダーリン。
(了)
小説部屋に戻る
|