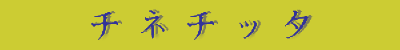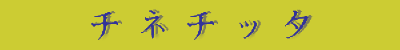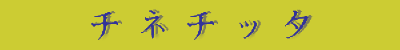
【チネチッタ】
ごろごろと暗雲の奥から雷が生じる音が聞こえる。もうじき雨が降ると首を天に見向け
たら、もうじきどころか雨は降り出し、徐々に私の背中、翼、尾を濡らしていく。でもあ
の人は大丈夫。私が自慢する立派な漆黒の翼が家となり、寝床となっているから。貴方は
安心してシーツに体を包ませて、寝息を立てれば良いのです。その寝息は私をもっともっ
と落ち着かせてくれる。夜盗が襲ってきても大丈夫です。任せてください。死なない程度
に鋭い牙を剥き出して追い払いますから。それとも、熱線は吐きませんから火の粉を降ら
して……あ、雨が降っているから駄目ですね。じゃあ牙で適当に噛み付いておきますから。
うん、大丈夫です。貴方は安心して、時々私の体に寄り添わせながら夢を見ていてくだ
さい。せめて、せめて、今だけは。明日また陽が昇れば、貴方は戦場を舞う若き英雄にな
る。英雄だと言われている。鉄と火が空を飛び交い、流れる血が地面の窪みに溜まり異臭
を放つ場所に果たして英雄は必要か。軍服に返り血を必要以上に浴びても、体をがちがち
震わせながら私に向かって「よくやった」と褒めてくれる貴方は決して英雄なんかじゃな
い。元はと言えば、貴方はストレスの塊みたいなもので、宿営での晩餐はいつも戻してば
かり。食も細くなり、平気顔で肉を喰らう仲間にからかわれても、やんわりとした顔で返
す。決して、英雄ではなく、ただの優しい人。時々、気が動転して、上半身を剥き出しに
しながら殺した人間の数だけ体中にナイフで傷をつける。返り血と己の血の判別なぞ土台
無理な状況で、貴方は泣きながらしゃがみ込む。そんな日もあった。そんな日は決まって、
見下ろしていた私を手招きして、顔を近づかせる。殺して、殺して、殺して、殺して、殺
して、と何度も何度も呟いて、私の頬を撫で回す。そう、貴方はただの優しい人。運悪く
英雄に奉られた十七歳の人間に過ぎない。
雨が強くなってきた。深緑の中にある我が軍部の宿営から、少しだけ離れている小高い
丘。トウキョウと呼ばれ、繁栄していた都市があったと史書の記述を読み聞かせてくれた。
丁度、私達の座っている小高い丘。初めて聞かされたときは非常に吃驚したのだけれど、
実は丘ではなくて物凄い大きな建造物の名残なんだとか。赤い骨組みの細長い建物はトウ
キョウ……タワーとかなんとか、そういう名前があって、何百年前に起こった戦争で壊さ
れてしまったそうだ。ところが今では、誰一人として原型を知る由も無く。ただただ、私
達の休んでいる場所は間違いなく、コケの茂った丘。森林から突き出ているような、私と
貴方様との束の間の憩い場です。丘の麓には、歪な円で出来ている湖が。私の大きな図体
も、勿論彼の体もスッポリと収めてくれる水浴び場。貴方は童心に返って、夕陽煌き、水
面が照らされる中をはしゃいでいた。ルカも入ろうよ、と言われたものだから私も厚い肌
を潤すために湖に身を沈めた。いやいや、待てよ。私の図体は軍部でも唯一無二の存在で
あるのは否めない、こんな私では彼が泳げるスペースが残ってるのかと思った。でも貴方
は何故か鼻歌交じりに泳ぎ続け、「気持ちいいね」。私に向けて、掌を組み合わせると、
水鉄砲を飛ばしてきた貴方の無邪気さが、己の翡翠の瞳にこびりついたまま離れなかった。
そう、すっかり泳ぎ疲れて、今、丘の上で一眠りしているのに至っていても。結局、乾
いた地肌を濡らさなくとも、私に関しては嫌と言うほど雨に打たれてしまっているけれど。
貴方のやんわりとした微笑を見る為に、ラメ色に輝き揺れる水面へ私は導かれるように
入っていったのだと結論付けたい。重圧に押し潰され、死臭に狂乱し、現実と虚構の狭間
でもがき苦しむ貴方を見つめて、私ももしかしたら、すっかり滅入ってしまっていたのだ
と。……安堵したかった。
雨が、止んだ。
蒼く太い首を、真っ直ぐに天高く伸ばし、曇り空の引いている夜空を見上げた。停戦協
定も今日一杯で切れて、明日からまた血生臭い進軍が始まる。望んでいない殺戮の令を受
け、私はきっと空高くからマジマジと人間たちを見据え、背びれを光らせ熱線を吐く。そ
れでも、また変わらずこの矮小な存在の為に、夜空が星をばら撒いてくれるのならば、ま
た変わらず貴方が私を相棒として頼ってくれるのならば、私は嬉々として躊躇わない。シ
ャカリキになって、戦場を舞うのだ。私はともかく、貴方の顔に死化粧は似合わないのだ
から。他者の血で塗られてゆく顔だけが、安泰。「やった、やった。良かったです。貴方
は全く萎えていない。張り詰めている。だったら、死にませんね。良かった! 今日も宿
営で寝られますね!」何もかもに攻め立てられる貴方を、私は精一杯に想い見守ることし
か出来ないけれど。
「誰かさんと、誰かさんがぁ……麦畑ぇ〜……」
寝言だ。貴方が口癖のように発する、いつかの時代に流行った歌詞の一端。一体何処か
らどのように伝承されたかは定かではないが、いつも満足そうに呟く。とうとう寝言にも
現われる。でももう起こさなければ。士官級の彼とて、軍の規律に反するならば“年上の
部下”にも示しがつかない。私は、彼の体を覆っていた翼を折り畳む。停戦協定の期限切
れまで、一時間を切っていた。再戦を祝して、丘の彼方に見える宿営テントからは、花火
が上っている。充分に生い茂っている森林を挟んで、充分に私達と宿営の距離もあるのに、
現実に引き戻されるには事足りていた。澄んだ夜空のもと、まだ夢の中で麦畑を駆け回っ
ている貴方に向けて、私は言い聞かせる。
麦畑なんて、無いですよ。
*
「そうだな。麦畑なんて無いよね」
ルカに囁き起こされた、前夜を想起する。それも敵軍と交戦の真っ只中である時に。在
るのは、鉄骨と呼ばれる骨組みが剥き出しになり、傾き、倒れているビルと呼ばれていた
遺跡群と、囲むのは広大で、殺伐とした湿地。そして僕は、今まさに敵軍将校を斬りつけ
捕らえているところ。ルカの熱線で特別に焼入れした刀は実に絶妙で、敵さんの足や腕の
一本や二本、朝飯前である。現に、捕らえた将校には両足が無かった。呆気無かった。た
だただ正面から撃ち、走ってくるだけなのだから、横に体を反らし身を翻して刀を抜けば、
それまでだった。僕は足無しの奥襟を掴み、ずるずると味方陣営まで引っ張ってくる。数
百ものビルから成る遺跡群は、丁度南北で相対するように、倒れている二棟の高層ビル(
ビルの最上級系?)が存在する。敵さんと我々は、暗黙の了解のうちにそれぞれを自陣に
している。我々軍部は、南だ。周りを囲む湿地帯が、遺跡の南側では若干侵食している。
地面もぬかるんでおり、移動にはやや不利。と、いうわけで戻って小休止を入れるつも
りが、早速敵さんたちに囲まれてしまったのである。我こそは! な気概がヒシヒシと伝
わっており、各々からは押すな押すなの大合唱。名誉を求めるだけの身勝手な数十人は、
奥襟を私に掴まれている足無し上司の事なぞ、恐らく眼中には無い。
「貴様らぁ! ワシが持っとるもんが見えんのかぁぁ!!!!」
とりあえず吼えてみた。でも相手からは怒号が変わらず聞こえるのみで、無視される。
ひとつ、深呼吸し、ハッとして空を見上げる。其処には背ビレを光らしながら、僕の真
上を旋回し続けているルカの姿があった。朴訥とし、凄惨な現場とは懸け離れた無表情を
浮かべる森の緑のように、優しい翡翠の瞳は、何処と無く落ち込んでいる。「大丈夫っす」
と僕は、首を横に振る。熱線の後ろ盾不要。とりあえず、止血なぞサラサラするつもりは
無かった、足無しは用済みになってしまった。即席の捕虜で敵さんの視線を釘付けにして、
纏めて片付けるつもりだったけれど。こうも野蛮人が多いと計算が狂う。それならば。
「ごめんなさい。将校さん。将校さんってだけで、貴方がどんな位にいるのかは知らないけれど」
文字通り、血の気が消えた足無しの顔から、ふと諦観したかのように笑みを零した。首
はすっかり傾き、視線も何処に見向いているのか分かりもしない。切り株となった両足か
ら止め処なく流れる血、血。もう駄目みたい。挙句、味方様からも無視されて。
「ちなみに僕は少佐です。この歳でですよ? バカみたいです」
僕は死に絶えている体を掴んでいた手を離す。どちゃりと、不愉快な音を立てて、足無
しは泥水に埋まる。無精髭とススだらけの顔は、口を必死に動かしているが、言葉を発せ
ずただただ泥を啜っているだけであった。僕は湿地に塗れ、黒を基調とはしなくなりつつ
あるブーツで、うつ伏せでもがく足無しを思い切り蹴り飛ばし、体を反転させる。もう、
口さえも動いていなかった。目は半開きで、白目を剥く。僕は刀を抜く。刀身に浮かぶ青
い刃紋と、そして己の表情。眉一つ微動だにさせない無表情に驚いた。咄嗟に、空いてる
掌で顔全体を揉みしだく。でも何も変わりはしない。僕は視線を落とす。ビルの“破片”
と雑草の入り混じる泥沼に浮かぶそれに、刀を垂直に向けた。一点に狙いを定めて……。
「うらぁぁぁぁぁぁ!!! くそったれがああああ!!」
僕を取り囲んでいた連中の一人が、耐えかねて飛び出してきた。
「うっせーわぁぁ! ぼけぇ! 黙ってろや!」
片手で握っている刀は狙いに定めたままで、もう一方は腰に装着していた革ホルダーか
らハンドガンを取り出す。迷わず撃った。連射、連射。弾が勿体無いから、出来れば数発
程度で済ませたかったけれど、最初の一発目がものの見事に額をぶち抜く。紅い飛沫が、
舞い散る。あとよく分からない神経やら脳の塊も一緒に飛び出た。顔面の原形を無くした
全身が痙攣し、後ろに倒れてゆく姿を確認するや否や、僕は一気に刀を足無しの胸辺りに
突き刺す。
「ガアアアアアアアァァァァ……ァ、ァッ……!」
突然の断末魔に、僕は激しい嫌悪を覚える。はらわたが煮えくり返った。何故今更、こ
んなにまで大声を張り上げることが出来るのか。気力があったのか。結局のところ、死に
絶えそうな様をわざと僕にぶつけていたのではないか。刀を握り締める力を強める。その
間にも、次々と堰を切ったように、飛び掛かってくる連中。僕は歯軋りをしながら、視線
は深く落としたまま。しかし泥が飛び跳ねる音を頼りに、銃を撃ち続ける。
「へっ、へへへへ」
僕は下衆な笑い声を発しながら、刀の柄をぐりぐり回す。
「お、おおお、おぅ、おぅ、げほぉぉ!!」
足無しは両目を完全に見開いたままで、口内に溜まっていた血塊を吐き出している。顔
を必至に右往左往させながら、身悶える。遂には全身を力一杯に揺すり、抵抗を試み始め
た。だが動けば動くほど、胸に突き刺さったままの刀に肉を裂かれるだけだった。段々と、
周りからの罵倒と泥水の不快音が聞こえなくなってきた。それでも僕は弾切れになる度に、
弾倉を取替え、また引き金を引き続ける。眼はずっと、ずっと、足無しの苦悶を捉えたま
まで。やがて念願の、潮時が訪れた。今度こそ奴は、身悶えるのを止め、弱りきった一面
を見せる。喘ぎも聞こえないものだから、僕は腰を屈め、奴の口元に耳を宛がう。
「い〜のち、み〜じか〜しぃ……。恋せぇ〜よ、乙女〜」
「ウッハ!! 死ねよ、死んじまえよ。ワシもアンタも女じゃねぇよ。何、歌ってるん?
なぁ、なぁぁって……!」
最後に発したのは、歌だった。いつだって人は死ぬ間際に歌うものだ。今までも、き
っとこれからも。僕が手に掛ける人間は、全て歌うのかもしれない。そして僕は、嘲笑い
続ける。その歌を歌う人間は、死ぬのだから。生き地獄を味わう我々とは違って、実に呑
気だ。僕は、足無しさんの存在を否定したく、腹を抱えて爆笑する。抱える腕と笑う唇は、
僅かに震えているけれど。
「……」
歌が止む。足無しさんは口端を満足そうに吊り上げると、笑ったまま死んだ。
「すまんけれど、気に食わないっす」
ハンドガンを奴の口内に力強く押し込んだ。前歯がへし折られる。少しだけ、銃口を上
顎に向けると、二発、発射した。今度はもう、断末魔は聞こえなかった。僕は自慢の蒼い
コート(ルカの体と同じ色!)に点々と付いてしまった、変な肉片を払い落とす。でも血
飛沫は拭いきれないので、思わず舌打ちをした。気分を変えて、僕は元気一発、顔を上げ
た。刹那、空に蒼白い光が走る。ルカの背ビレが発光したと思ったら、口を大きく開け、
一気に体内に留めていた熱線を放射した。一直線に、ひたすら一直線に、北へ、北へ。途
中を阻もうとする遺跡であるビルを粉々に吹き飛ばす。稲光にも似た其れは、ギザギザに
揺れ動きながら、そしてとうとう高層ビルを打ち砕いた。途端に響く慟哭。真っ二つに折
れ、まるで紙吹雪のように舞う、ざらついた硝子の破片。突如として火の手が上がる。僕
は含み笑いをしながら、静かに跪いた。膝から染み込む泥水が気持ち悪い。追い込まれて
いるのは彼ら、北側の人間であることは明瞭だった。この世でただ一匹の怪獣を連れ添っ
ている、我々の部隊とぶち当たった連中には死刑宣告が言い渡されたのも同じだからだ。
ルカの背ビレが光った瞬間に、放たれる熱線のたった一発がどれほどの威力を見せるの
か、双方共々、重々に分かりきっている。まさしくたった今、示された。僕は頭を垂らし、
両腕でしっかりと全身を抱き締める。握り拳に、コートのしわが寄る。また一発、一発、
頭上高いところで、花火が舞う。僕が一番、安心する瞬間。勝利が輝かしい色を帯び、眼
前に提示される喜び。僕の周りを囲んでいた連中も敗北を確信していた。もうとっくに。
しかしもう、何としてでも攻め入り、飼い主の僕を捕らえることしか、考えるしかなか
ったのか。
「ずるいですよ、本当にずるい。もしオレがあいつの飼い主だったら、こんな場所でも酒
を片手に大はしゃぎさ」
彼らは口々に羨望を述べると、跪いている僕からハンドガンを取り上げると、次々にこ
めかみに宛がう。花火、銃声、花火、銃声、花火、銃声、花火、銃声……。笑いが止まら
なかった。抱き締めていた体をぐらつかせ、ピンク色の何かと、血が入り混じっている地
面に横たわる。
「フヒヒヒヒッ、アハハハハハハハハハハハ……」
顔を歪ませていたら、ついでに涙も止まらなくなった。もう僕の視界には、滲んだ世界
が広がるだけ。
「フフフフッ、ルカ、ルカ、ルカ、ルカァァァァァァ!!!」
彼の名を呼ぶ。僕を理解し、寄り添ってくれるたった一匹の存在。体を丸めて、ひたす
ら泣き叫んだ。ルカと同じ色で新調したコートも、その下に在る軍服も、自分の肌と赤い
髪を、汚くして。意に沿わない罵言を浴びせ続けた己を呪う。でもまだ続く。これからも
ずっとだから。だから。
生き抜くために殺して、殺すために生き抜くよ。狂気の沙汰とは言わんでおくれ。
「誰かさんとぉ、誰かさんが、麦畑ぇ〜、ちゅーちゅっちゅっしている、いいじゃないか〜♪
僕には恋人ないけれどぉ〜……、いつかは誰かさんと、麦畑ぇ……」
*
貴方はやっぱり優しい人だ。心の奥底で罪悪感が蠢いている。だから泣いてしまう。貴
方は、私たちで言う雌を愛したことが無い。私だけを愛してくれた。赤い髪はね、僕たち
被差別民族の象徴なんだよと教えてくれたとき、「そんなの嘘です。綺麗じゃないですか
」と首を横に振った。貴方は瞳を潤ませて、私の頬に、鱗肌に口づけをした。笑顔が見た
い。切れ目をぎらつかせて、刀と銃を暴虐に扱う貴方は、ただ自分を真っ黒いヴェールに
包ませているだけ。私には罪悪感が残念ながらありません。北から黒煙が立ち込め、味方
含め、何人の人間を焼き尽くしたか想像にし難い。私は熱線を吐く。遺跡と、木々が瞬く
間に仰け反る。そして灰に。南の高層ビルで固まっていた方々は嬉しそうに、持ち込んだ
杯を交わす。各々がビルの断片に座り、拍手喝采を送る。私は慌てて、貴方の様子を伺う。
耳を澄ます。生気の萎えた表情と、僅かにびくついている全身。ひっそりと横たわる貴
方。そして微かに聞こえるあの歌。
私は恋人にはなれないけれど、麦畑くらいなら探せますよ。躊躇いは無用だった。私は
怪獣。怪獣と呼ばれる存在。戦争と呼ばれる歴史に用いられるだけの存在。でも貴方は私
だけを愛してくれた。そう一心に。そして貴方は私しか、恋人と呼べるものを見つけられ
なかった。私は、再び戦火で揺らぐ森林と遺跡を見渡した。橙とも朱色とも呼べる辺り一
面と、時折混じる絶叫。心身が打ち震える。生きている。生きている。皆は死ぬが、私と
貴方は生きている。ごめんなさい、あともう一回、許してください。すぐ迎えに行きます。
そうしたら、そうしたら、また笑ってくれますよね。
「ッッッッッッ―――――!!!」
私は牙を剥きながら、声高々に咆哮する。両翼を今一度ピンッと張る。背ビレがむず痒
い。何回目とも知らない、安堵のための雷(いかずち)が解き放たれるまで、私は静かに
目を閉じる。自分だけの歌声を、ひたすら、ひたすら探っていた。
「誰かさんと、誰かさんが……」
(了)
<小説サイトThe
back of beyond's様主催 夏のコラスペ08 第4位選出作品>
小説部屋に戻る
|